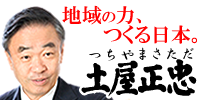再掲「日弁連副会長以下5人、平和安全法制に反対の申し入れ―私は『憲法守って国滅ぶでは困ります。歴代の為政者は憲法解釈を時代に応じて変更し、我が国の存立と国民の安全を守ってきた』と申しあげた」
(2015年6月21日のブログより)
先週の金曜日、日本弁護士会三宅副会長以下5名の弁護士さんが訪ねてこられ、平和安全法制整備法は反対だ、著名な憲法学者も違憲と言っているとの主張。
(土屋)歴代の為政者は日本国憲法の変更は難しいのでその都度憲法解釈を変更して国際情勢に対応してきました。一番大きな変更は吉田茂首相の変更です。
当初「一切の軍備は持てない」と発言していましたが、朝鮮戦争が始まると「自衛のための戦力は持てる」と自らの答弁を否定し、憲法解釈を変更しました。
その後1960年日米安保条約を改定し、日米で軍事同盟を締結し集団的自衛権に一歩踏み出しました。
(日弁連)日米安保条約は米国に日本の防衛の責務を課したもので、日本は米軍の基地提供が義務付けられて米国防衛の義務が無い片務的なものです。
(土屋)片務的な条約とよく表現されますが、日米が対等に結んだ条約ですから、今では米国の武力行使による防衛と、基地提供という非対称的責務を負う双務的軍事同盟と解釈されるのではないですか?
(日弁連)憲法審査会では自民党推薦の長谷部恭男さんも違憲と主張していました。
(土屋)長谷部氏は昔自衛隊も違憲と言っていましたが、憲法審査会では合憲のような主張でした。
(日弁連)砂川判決などを受けて情勢に合わせて主張されているのだと思います 。
(土屋)自衛隊違憲を合憲と変えたのなら憲法の解釈変更ではありませんか。
(土屋)民主党推薦の小林節氏は著書「憲法守って国滅ぶ」の中で大切なのは国の安全だ。
憲法が改正できなければ解釈を変えれば良いと主張されていました。(本を示して申しあげた)
(日弁連)砂川事件について一審の所謂伊達判決から最高裁判決まで通して読みましたが、集団的自衛権行使を容認した記述はありません。
(土屋)田中耕太郎最高裁長官の補足意見の中には集団的自衛権について触れられています。
(日弁連)補足意見はあくまでも補足意見で判例集にも残っていません。
(土屋)多数決で決まった時、反対は「少数意見」、賛成は「意見」とされますが、この判決は15人の裁判官全員一致です。その上で最高裁判決の背景を述べたのが「補足意見」ではないのですか。
(日弁連)当時は自衛隊が無かったので米国の抑止力を認めたのです。
(土屋)当時既に自衛隊はありました。
※注:砂川判決は昭和34年。自衛隊は昭和29年(前身の警察予備隊は昭和25年)発足。
(日弁連)失礼。間違えました。
(土屋)専門家の皆様にお聞きしたいのですが、昭和34年の最高裁判決以外に集団的自衛権について述べた確定判決はあるのでしょうか。
(日弁連)ありません。集団的自衛権は昭和47年政府見解に従って考えるべきです。
(土屋)国際情勢が著しく変化し、脅威が増しています。国の存立と国民の安全を守るために、憲法9条の枠内で可能な限り現状に合わすべきです。