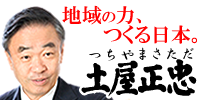憲法改正か解釈改憲か。5月3日の憲法記念日近づく
昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されてから78年目を迎えます。
当時は米国と米軍を中心とした連合国による占領下であり、日本の主権は制限されていました。国家主権が連合国の隷属下にあった中で、戦後の新憲法が大日本帝国憲法の全面改正という形で国会で可決、公布されたので、正統性はあるのか?サンフランシスコ平和条約が締結された時に破棄されるべきだったのでは?という根本議論が長年続けられてきました。
第二次世界大戦後に米ソ対立が明らかになり、世界は二つの陣営に分断されました。覇権争いが繰り広げられ、軍事的緊張が高まり、日本国憲法の制定当時と状況が大きく変化してきました。
一方、日本国憲法の改正は、衆・参両議院の2/3賛成により発議し、国民投票に付し、半数の賛成を得なければ改正できない「硬性憲法」であります。憲法改正のハードルが高いので、世界の実情に合わせて憲法解釈を変更せざるを得なくなりました。それが解釈改憲です。
戦後最大の解釈改憲を行ったのが、吉田茂首相でした。当初「現憲法下では、一切の軍備を持てない」との解釈を、「国家存続のために必要な最小限度の自衛の組織は持てる」と解釈変更したのです。昭和25(1950)年の朝鮮戦争をきっかけに「警察予備隊」「保安隊」「陸上自衛隊」に発展する根拠になりました。
それ以後、世界の実情に合わせて内閣が主導して、憲法解釈を変更する「解釈改憲」を行って来ました。直近では、安倍晋三首相の下で行った平成27(2015)年9月の「平和安保法制」です。集団的自衛権を限定的に認めた解釈改憲です。国会で自衛隊法改正と必要な新法が成立しました。
米国にトランプ大統領が誕生して「アメリカは世界各国から経済的に搾取されている」と主張し、関税戦争が始まっています。アメリカ第一主義は経済および軍事の両面に及んでいます。オバマ大統領の時代に「アメリカは世界の警察官を辞める」という方針の延長にあるように思われます。
日本も独立と平和を守るため、どのような防衛政策を取るのか迫られています。2年後に憲法施行80年を迎えます。憲法改正をいよいよ本格議論しなければならない時を迎えています。