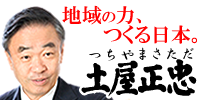福島原発視察。武蔵野・西東京・府中・三鷹市の各市議等17名で-処理水の海洋放出が軌道に乗り、炉内のデブリ除去に向けて実証実験が続く
百聞は一見に如かず!4/4(金)武蔵野市周辺の市議等に呼びかけて、福島原発の廃炉作業の現場を日帰りで視察した。
朝7:52東京駅から常磐線の特急に乗り3時間。大熊町の冨岡駅に着いた。12時から廃炉資料館を見学して事故の概略を受け、福島第一原発の現場へ。放射能管理区域内に入るには身分証明から始まって厳しいチェックを受け、個人別放射線量計を着ける。除染が進み2016年から放射能防護服を着用しなくても現場近くまで行けることになった。
原発事故の要締は、止める・冷やす・閉じ込めるだが、2011年3月11日の東日本大震災にともなう津波による全電源喪失で冷却水が循環出来なくなり、冷却できず2000℃を超える高熱によりメルトダウンした炉の廃炉作業にかかっている。
1~4号機の前に立つ。それまでゼロに近かった線量計が反応する。炉から80mの場所の見学用に作られた台に備えつけられた線量計が43マイクロシーベルト/hを示していた。
汚染水をALPS(多核種除去設備)で処理した処理水をIAEAの国際基準の1/40に稀釈して、1km沖まで導引して海中に放流する工程は、水産物に影響がないことが証明され、地元漁港をはじめ全国の水産業者の理解を得て、着実に放流作業を続けているとのこと。軌道に乗ったとはいえ、計画によるとこれから30年間続くという。
これからの最大の課題はメルトダウンしたデブリの取り出しだが、去年初めて少量の取り出しに成功した。小さな一歩だが、ひとつひとつの検証を重ねて、改良を加え、本格的なデブリ撤去につなげたいとのこと。
5年前に総務省から派遣された福島県の幹部と二人で視察してから、回を重ねて4回目の視察となった。視察するたびに、除染区域が減少しつつある。
さらに大熊町の冨岡駅近くに設置されたスーパーとドラッグストアと食堂のサクラモールがある。5年前より商品の品数も増え、人々が集まり、賑わいを取り戻しつつあると実感した。