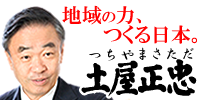九州豪雨1時間100㎜超の雨、これでは決壊するー50年前に武蔵野市役所に入った時の河川や下水の整備目標は1時間30㎜だった
九州全域に線状降水帯がかかり河川が氾濫して大勢の犠牲者が出ている。時間100㎜超の猛烈な雨だ。昭和30年代にまだ下水が整備されていない時代、台風が来ると武蔵野市内の低地は各所で氾濫し住宅地や畑が水浸しになった。吉祥寺北町の一角には井之頭公園からボートを持って来て救助に当たったことを子ども心に記憶している。昭和41年武蔵野市役所に就職した時土木職の合言葉は武蔵野を水害から守るため1日も早く下水道を普及して時間30㎜豪雨にも耐えられるようにしようという目標だった。現在は50㎜対応を目標にしている。まだ未達成だ。
九州各地に振り続ける雨量が時間100㎜を超えたり24時間で500㎜と報道されている。想像を絶する雨量だ。今はただただ雨が止むのを期待するしかないが現地の被災された方々を始め救援に赴く消防、警察、自衛隊、医師を始め医療関係者の無事を祈るばかりだ。
自民党も令和2年豪雨対策本部を先週末に設置し二階幹事長が本部長となり7月6日(月)から会合を開き政府に迅速かつ十分な対策を求めました。政府・与党一丸となって災害対策に取り組みます。